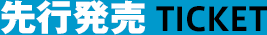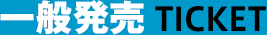The Stranglers
Live In Japan 2019
2019.11.03 sun. 渋谷 WWW
open 17:30 / start 18:00

レジェンド・オブ・パンク27年ぶりの単独来日公演!
伝説の“理由”と“再燃”を目の当たりにした衝撃の一夜!!
単独公演としては27年ぶりとなる、ザ・ストラングラーズの来日公演[LIVE IN JAPAN 2019]。結成から45年の長きに渡り挑戦を止めることなく走り続けてきた、まさしくレジェンドである。その名は初期パンクの枠に止まらず、その後のポストパンクや広くロックシーンへと幅を広げ、いまだ世界中で厚い支持を受け続ける。そんな彼らのステージが、今回の来日公演ではキャパシティー500〜600人という会場で3デイズに分けて行われるという。その初日を飾るのは渋谷WWW。目の前にそびえるステージ機材、その背面で威容を放つ巨大フラッグ。手が届きそうな距離でのステージの存在感が、本ツアーの贅沢なスペシャリティーを大いに実感させる。
ファッションやヘアスタイルなど、思い思いの形でアイデンティティーを表現する粋な紳士・淑女たちで埋め尽くされたフロア。ソールドアウトの会場に静かな熱気が充満する中、定刻より10分を経て暗転、異空間へと導く怪しげなワルツとともに遂にメンバーが登場する。ステージまでわずか数メートル、目の前でおもむろにベースを突き出したBa.&Vo.ジャン=ジャック・バーネル(以下JJ)が、その代名詞ともいえる雷鳴のごときビートを刻む。その凄まじい衝撃に撃ち抜かれたオーディエンスは、一瞬でそれぞれのパンク原体験の当時へとフッ飛ばされる。かつてのパンクスたちが野生を取り戻すには充分すぎる破壊力だ。フロアのリアクションを見て、笑みを讃えるJJ。この日が間違いなく素晴らしい夜になることを予感させる『Toiler on the Sea』で幕開けだ。

1978年のアルバム[Black and White]収録曲で幕を開けたかと思えば、起伏に飛んだ現代的なアレンジが情景を疾駆させる『I’ve Been Wild』は2004年発表アルバム[Norfolk Coast]収録曲。続くは1stアルバム[夜獣の館]より、ダンスミュージックに対するパンクからの解答を叩きつけた『(Get a)Grip(on Yourself)』を投下。躍動するビートの上に構築されるKey.デイブ・グリーンフィールドのクラシカルで荘厳な音壁。会場は狂乱のダンスフロアと化す。
ド頭3曲でいきなりピークへと押し上げられたオーディエンスは、『Time To Die』から、さらにバンドの深淵なる世界へと引き摺りこまれる。剥き出しの衝動を解放しながらも、耽美で退廃的な危うさが共存したムードはザ・ストラングラーズならではの世界観。続く『Nice ‘n’ Sleazy』では、Vo.&Gt.バズ・ワーンとJJがステージから身を乗り出し、舐めるようにフロアを見回す。その狂気を帯びた眼に狂喜で応えるオーディエンス、空間は非日常へとひたすら加速していく。

バズといえば、2000年にザ・ストラングラーズにギタリストとして加入。そして、JJとともにバンドの中心人物でありながらも1990年に脱退したVo.&Gt.ヒュー・コーンウェル、そして後任のVo.ポール・ロバーツを経て、2006年からはリードボーカルを兼任する。昔ながらのファンにとっては、彼が歌う往年の名曲への印象も大いに気になる点であったはず。だが、大柄な体躯とスキンヘッドというルックスは存在感抜群にして、真摯に歌い上げる姿は目と耳と心をグッと引き寄せる。そして、豊かな低音から熱のこもった高揚感まで、鮮明に歌世界を浮かび上がらせる歌唱で魅了していく。伝説的バンドのフロントマンとして、その重責を担いながらも彼ならではの艶と温度をバンドに注ぐ、堂々たるパフォーマンスだ。
体調不良のため近年はライブから遠ざかってしまっているジェット・ブラックに代わるDr.ジム・マコーレーが力強いビートを繰り出す。自然に巻き起こったハンドクラップが嵐のような喝采に変わった『5 Minutes』では、御歳70才のデイブがビールを片手に飄々とホンキートンク風味のロックンロールピアノを打ち鳴らす。そして怒声のような鋭さを持ったJJのシャウトボーカルが大合唱を誘発。続く『Unbroken』でも、JJは巧みにステップを踏みながら、剛柔と緩急を使い分けるボーカルで沸かせる。
冒頭でも述べたが、破裂音と図太さを両立させたJJのベースプレイをこの距離で体感できるのは本当に貴重だ。ザ・ストラングラーズ以降のポストパンク〜オルタナティブミュージックへと継承されていく独特なベースサウンドは、2019年の現在でも色褪せない衝撃を放つ。その唯一無比なるサウンドもさることながら、中心人物としてバンドを動かし続けたJJの存在感、求心力の凄さを改めて実感する。

この日のメニューは新旧お構いなしにシャッフルされた構成だったが、テンションや世界観の一貫性を根底に感じさせながら、様々な楽曲が畳み掛けられていく。確固たるオリジナリティーを持ったバンドのみが成せる特権というべきか。
これといったインターバルもMCも入れず、ひたすらに楽曲の世界観を見せつけるステージ。その姿は粛々としながらも、百戦錬磨のライブバンドから滲み出るオーラが目を釘付けにする。キャリア最大のヒット曲とされる『Golden Brown』では、物哀しいチェンバロの音色が空間を染め上げる中、目を瞑って耽美な世界を表現するバズ。そのスキンヘッドに浮かぶ汗を拭うJJ…そんな余裕を垣間見せる一幕もご愛嬌だ。『Always the Sun』や『Skin Deep』では、中期ザ・ストラングラーズの80年代的な質感がカラッとした新鮮な風を吹かせ、時代の流れやバンドの音楽性の変遷を感じさせる。
ライブの中軸として重厚な存在感を放ったのは、射すくめるようなバズの眼光が印象的だった『Peaches』。そして来日のプレゼントとして急遽メニューに組み込まれたのか、演奏後の安堵した表情も印象的だった『Outside Tokyo』。ショウマンシップとさりげないサービス精神が、この日のスペシャリティーをより一層高めていく。
ここまで息をつかせぬままに約1時間。やっとMCタイムらしいインターバルを迎えるが、終始グビリと飲っていたデイブ以外にとっては“カンパイ”タイム。「これはYEBISUじゃない! 俺はYEBISUが欲しいんだ!」と声を荒げてみせるJJ。笑顔がステージとフロアの垣根を取っ払い、一体感を増した空間は終盤へ向けてさらに狂騒を高めていく。

デイブのサイケデリックなオルガンサウンドが脳をくすぐる名カヴァー『Walk On By』、ノドを枯らした“チェンジ!”の連呼がフロア中を飛び交う『Something Better Change』、歌とキーボードのドラマティックな調和が胸を焦がす『Relentless』。怒涛の3連発で大喝采に包まれるも、まだまだブチ込まれる着火剤。『Hanging Around』ではバズの性急なボーカリゼーションがオーディエンスの合唱を煽り立て、全てをなぎ倒すような重戦車ビートが圧巻の『Tank』では轟く爆発音がリアルに会場を震わせる。そして凄まじい爆音の残響を残し、メンバーは退場。大充実の本編を終えてもなお加熱を続けるオーディエンスからは、咆哮のようなストラングラーズコールが響き渡る。
JJを筆頭に再び登場したメンバー。士道館空手英国支部の師範館長としても知られるJJは「アリガトーゴザイマシタ。ニホンゴスコシワカリマス。押忍!」と流暢な日本語を披露。
そしてアンコールは2曲。煌びやかでポップなロックンロールにアイロニカルな毒を過剰投与した『Duchess』、続くオーラスはもちろんこの曲、初期UKパンク史に燦然と輝く名曲の一つ『No More Heroes』だ。多くのオーディエンスがフルコーラスで絶唱し、粋なパンク紳士によるポゴダンスがそこかしこで弾け飛ぶ。最高すぎる光景とともにこの日の最高潮を迎える。オーディエンスの上気した笑顔、そしてその先に見える偉大なミュージシャンたちの飾らない笑顔。同じ悦びと興奮を共有していたという実感、多幸感溢れる会場の空気に胸を熱くしながら、至福のひと時は幕を閉じた。
これぞレジェンド・オブ・パンク、その一言に尽きるステージだった。ド頭の一音で全身を貫いた衝撃はそのままラストまで、絶えることのない合唱と突き上がる拳に彩られた。時代は移ろえども、それぞれの時代において鮮烈な衝動を投下してきた功績を実感し、今もって新たな創造と表現を研ぎ澄ます姿勢は感動を呼ぶ。伝説の理由、そしてその再燃を目の当たりにした一夜だった。
[TEXT by Go Nemoto]
[PHOTO by Hiroki NISHIOKA] ※写真は11/3&11/4両日