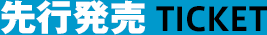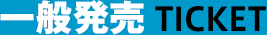Atomic Skipper pre FREE LIVE EVENT「人間讃歌」
【出演者】Atomic Skipper / アメノイロ。/ Organic Call / プッシュプルポット
2022.7.26 tue at duo MUSIC EXCHANGE
open 17:30 / start 18:00

Atomic Skipper初のフリーイベント開催
実力派ライブバンド4組による伝説の幕開け
この日、渋谷duo MUSIC EXCHANGEには、ネクストブレイクアーティストとして注目される実力派の4バンドが集結。オープン前にも関わらず、会場入り口付近には、多くの若者たちが長蛇の列を作っている。向かう先は[Atomic Skipper pre FREE LIVE EVENT「人間讃歌」]と題された大型フリーライブイベント、首謀者たるバンドはAtomic Skipper。今年春には渋谷Spotify O-Crestでのワンマンライブを完売させ、今回、バンドにとって初となるフリーライブイベントを開催。しかもキャリア最大規模であるduo MUSIC EXCHANGEを、平日ながらも見事にソールドアウトさせてしまっていた。バンドの勢いを目に見える形で次々と体現させ、若きロックシーンにおける最重要バンドと言っても過言でないだろう。
入場者数の規制緩和も相まって、会場内にはコロナ禍以前のライブハウスに少しだけ戻ったような、賑わいのある景色が広がる。もちろん入場時の検温・消毒は徹底され、皆一様のマスク姿ではあるが、テンションの高ぶりは明確に伝わってくる。そんなオーディエンスの前に最初に躍り出たのはOrganic Callだ。

力強くダイナミックに打ち鳴らされるボトムに支えられ、スケール感のある艶やかなギターやコーラスが、美しく雄大な景色を描いていく。平田真也[Vo, Gt]の深みを伴った独特の声音は耳なじみがよく、メロディと言葉が自然と溶け合ったような魅力がある。オーディエンスの耳目と心を惹きつけ、一気にライブハウスならではの空間へと没入させていく。
「この4バンドが無料で観れてしまうという最高のイベントだと思ってます。俺らもアトスキ(Atomic Skipper)が超好きです。でも好きだけじゃ終わらせたくない、そんな仲間でもあります。目の前にいる一人一人に、真っ直ぐロックバンドの歌を届けに来ました」
『朝焼けに染まった街へ』では、オレンジに染め上げられたステージで全身を振り絞るかのように歌を響かせ、『愛おしき日々たちへ』ではメンバー4人のテンションが交錯する圧巻のステージングにフロアが沸き立つ。「最高の始まりだ!」と吠えた平田の言葉通り、30分のステージに全身全霊を注ぎ込み、トップバッターとしてこの上ない、ヒリつくようなライブの熱気を充満させたステージであった。

続くは広島・尾道出身のアメノイロ。が登場。「イベント[人間讃歌]に呼んでくれて、仲間に入れてくれてありがとう。このメンツで、なんでアメノイロ。を呼んでくれたんだろうって考えてたんですけど…」という寺見幸輝[Gt.Vo]のMCとは裏腹に、そのステージにはオーディエンスの盛大なハンドクラップが終始鳴り響き、研ぎ澄まされたバンドアンサンブルと相まって、スケールの大きなライブ空間を構築していく。ソリッドなリズム隊のプレイを感じながら、しなやかに踊るような寺見のボーカリゼーション。その柔らかく澄んだ歌声に絡みながら、豊かな彩りを加えてく木村洸貴のギタープレイも絶妙だ。
「不安で不安で眠れない夜、どこまでも寄り添えるバンドでありますように」というMCからの『眠る前に』ではグンとギアを上げ、加速するビートに乗った寺見の歌にエッジが立つ。続く『あとがき』では、時に切れ味鋭く、時に温かく包み込むような巧みな緩急がフロアを掻き回す。シンプルながらも練られた楽曲、それをライブでより立体的に響かせるパフォーマンス、そこには彼らが音楽に真摯に向き合う姿や音楽愛が如実に伝わってくる。そして彼らの本気と愛が、フロアにじんわり染み出していくような、爽快な高揚感と温もりをもらったステージだった。

「ヤバいとこ見たいかい!? 行くぜー!」という咆哮一発、シンガロングなコーラスワークが効いた楽曲で瞬時に会場を強固な一枚岩へと化したのは、金沢から全国区へと躍り出たプッシュプルポット。キャッチーさと突き抜けた爆発力によって放たれた、山口大貴[Vo, Gt]の真っ直ぐな歌は、ステージと客席の隔たりを突き壊し、オーディエンスの心を目がけて一直線にブッ刺さる。
明るくヤンチャな爆進を続けるかと思えば、「今日のこの一瞬とか忘れたくないよ。いつもありがとう。居場所くれてありがとう。面と向き合ってくれてありがとう。忘れたくないから、忘れないように歌を歌って帰ります」と、それまでの空気から一転、切なさを孕んだ思いを吐露し、プレイされたのは『13歳の夜』。過去の痛みがあるからこそ、今を大切に噛み締め、前へと進む、「今日も僕は支えられながら生きてる」と歌われる名曲で一気に感動モードへと叩き込み、そしてラストに向かって、よりエモーショナルな側面を剥き出しに。高速ナンバー『snooze』で愚直とも言える勢いを爆発し、さらにトドメの人気曲『笑って』できっちり“ヤバいとこ”へとオーディエンスを連れて行った。彼らからほとばしるピュアさは絶大なる説得力を生み、美しく、そして無敵である。

フリーライブイベント[人間讃歌]、いよいよそのラストを飾るAtomic Skipperが登場だ。中野未悠[Vo]が高らかに拳を上げれば、フロアに浮かび上がる無数の拳の数々。荘厳にして堂々たる『シンガロングは夢を見る』でこの日のライブは始まった。
急激にビートを加速させ、次曲『幸福論』では神門弘也[Gt&Cho]と久米利弥[Ba&Cho]がハジケるようにステージ両端へ。中野はド頭からオーディエンスを強制的にトップギアへと叩き込むかのごとく煽り立てる。「もう始まってるぜ! 飛ばせ飛ばせ!」とアネゴ肌なアオリ文句も堂にいったものだが、ド迫力の声量や細やかな歌表現といった、ボーカリストとしての抜群の技量が何にも勝る特効薬。すでにフロアは、ワンマンライブのごとくの有り様へと変貌していた。
そんな彼女の歌ヂカラをガツンと見せつけられたのは『アルテミス』。序盤に近い位置でしっとりと聴かせるミディアムナンバーが登場したことに意外性もあったが、ファルセットを駆使した幅広い音程で魅了する歌い回しや、言葉や感情をグッと押し出す表現力が、理屈や形式など関係なしに突き刺さる。また、松本和希[Dr&Cho]のドラミングをはじめ、歌に寄り添った楽器陣の細やかなニュアンスによる表現も明確に伝わる一幕だった。
そして中盤では、今年6月からスタートした3作連続配信シングルの第二弾としてリリースされた『ブルー・シー・ブルー』(7月20日発表)を披露。このライブの時点では発表からまだ1週間程度しか経っていない新曲なのだが、瑞々しく伸びやかな旋律はファンの心にしっかり刻み込まれている様子だ。続く『メイビー』では、より凄みを感じさせるエモーショナルな歌声とコーラスワークの重厚な響きが否応なく熱量を上昇させ、自然に巻き起こるハンドクラップとの一体感も心地良い。メンバー自身も心底楽しんでる様子がそのパフォーマンスに溢れ出し、広いステージで所狭しと躍動する。

ここまで渾身の歌声を響かせてきた中野だが、さすがは百戦錬磨のライブバンドである、終盤でもその歌は健在。イベントタイトルにもなった『人間讃歌』のイントロでは、アカペラ的アプローチでの美声が温かくも力強く、息を飲むような迫力で会場を包む。
「マジで伝説的な日になりました。ライブハウスで生き続けてきたから、キミたちと向き合い続けてきたから、プッシュプルポット、アメノイロ。、Organic Call、あの3バンドと正々堂々、音交わして来たから、そして今、揺るがない自信みたいなものがあるから。だから今日、意義のあるイベントなったなって思ってる。見えない価値があるから。今日感じ取ったものを持って帰ってさ、またライブハウスで会おうよ。そのための今日だ!」
6月15日発表の連続配信シングル第一弾『tender』では速射砲のように放たれる言葉を、豊かな声音や歌い回しに加え、表情や細かな身振りとともにリズミックに表現。そして本編ラストは、バンドマンとしての誇りと決意を高らかに叫ぶ『ロックバンドなら』。メンバーそれぞれの全力のパフォーマンスが破壊力抜群のバンドグルーヴとなって脈打つ。それに反応するオーディエンスの熱量も凄まじく、気持ちの交換が美しい大団円へと繋がっていく。
その後、わずかなインターバルを経て、アンコールでは『動物的生活』をプレイ。会場に充満した熱気が清々しい後味に変わるような爽快さをもって、Atomic Skipper初のフリーライブイベントは大盛況、大熱狂にて幕を閉じた。
四者四様の魅せ方、そしてそれぞれに本気を出し尽くしたステージで、見事なまでに会場を沸かせてきたフリーライブイベント[人間讃歌]。“伝説的な日”は、出演した4バンドにとって、また新たな伝説へと向かう、始まりの一日でもある。今年秋にはAtomic Skipper東名阪ツアー[3ヶ月連続配信シングルリリース企画「再会と相対」]を予定し、同ツアーファイナルが11月1日(火)CLUB QUATTROであることがアナウンスされた。また規模が大きくなった発表に嬉しい驚きをもたらしたが、そこでもやはりAtomic Skipperは一回りも二回りもデカくなったステージを繰り広げることだろう。そしてさらにもっと先の未来まで確かな期待を抱かせるに十分なほど、次代のロックシーンを担う若きバンドたちの実力と才能に魅了された一日だった。

[TEXT by GO NEMOTO]
[PHOTOS by nishinaga “saicho” isao]