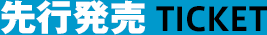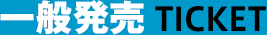PAUL WELLER
PAUL WELLER JAPAN 2012
2012.10,27 sun at Zepp DiverCity
open 17:00 / start 18:00

英国が誇るロック界の兄貴が来日!
挑戦の果てを見せる貫禄のライブ!!
The Modfather”の来日である。元OASISのノエル・ギャラガーが”俺のベスト・メイトはポール・ウェラーとザ・スミスのジョニー・マーだ”と公言し、90年代以降に世を席巻したプリットポップシーンをはじめ、数多くの若き一線級ミュージシャンからアニキ的存在として信奉されているUKロック界の”顔役”、ポール・ウェラーの約3年ぶりとなる来日ツアー、その最終公演だ。
会場となるZEPPは、実物大ガンダムがそびえ立つ東京の新名所・ダイバーシティ東京の一角にある。週末ともなれば、家族連れ、カップル、そしてガンダムファンと、とにかく人・人・人である。限られた休暇、当たり前に混雑する新名所、庶民も大変である。しかしこの日はそんな群衆に入り混じって、粋なタイトスーツや、コジャレたUKフットボールウェア、そしてややカジュアルなパンクファッションなど、ひと味違う主張をまとった人々の姿もチラホラ。人混みを掻き分け掻き分け、時にガンダムをチラ見し、ダイバーシティに奥地に辿り着くと、多くの音楽愛好家が列を成してゴッタ返していた。うむ、アガる。
今回のポール・ウェラー・ジャパンツアー東京公演はZEPPダイバーシティで3デイズとなるわけだが、この日は唯一の週末公演というわけで、早々に全席がソールドアウトとなっていた。会場は2階席まで2000人超の人でギッチリ埋まり、改めてその人気の高さ、そして根強さに感心させられる。また今ツアーでは、各公演でサポートアクトを起用したこともチケットの動きに拍車を掛けた要因だろう。この日のサポートはくるりだった。
「京都から来たくるりです」というサラりとしたMCで、ほぼ開演時間定刻にライブはスタート。くるりといえば、日本人の心のヒダにじんわり染み入るようなメロディと、挑戦的かつ斬新なアプローチや曲構成が特徴的だが、それがポール・ウェラーのファンにどう捉えられるか、実は興味深かった。お国柄は違えと、郷愁的であったり叙情的な心の琴線に触れる旋律というのは多くのイギリスの音楽には特徴的だし、挑戦的かつ斬新なアプローチというのも、ポール・ウェラーがその永いキャリアの中でさんざん見せつけてきた姿勢の一つと言える。なかなか心憎いマッチメイクじゃないか。約30分のライブだったが、各曲演奏終わりでの拍手が会場の後ろへ後ろへと規模を広げていき、そのサウンドが浸透していくのが見て取れる。邦楽は門前払い的に一切興味がない、という洋楽ファンも少なからずだろうし、逆もまた然りだろう。しかし、批判は大いに結構だが、聴かず嫌い的な表層的な壁にはお互いどんどん風穴を空けてほしいし、そういう意味でもこういう機会は大切だと思う。音楽産業が衰退の一途を見せている現在、”良い音楽”が深みと広がりを得るためにも、壁のない土俵でもっと切磋琢磨されて欲しいなぁ〜。なんてね。

はてさて、くるりのライブ終了後、照明トラブルの対処なんぞもあって、たっぷり30分のインターバルを置くことに。”早くやれ! 遅せぇぞ!”なんてヤジも飛び、その出どころに嫌悪感たっぷりの目を向ける紳士淑女もいる。会場には、本当に様々なバックボーンを持った人々が混在する。なんせ35年のキャリアである。77年デビューのThe Jam(当時ポール・ウェラーは17歳!)では、パンクロックからR&Bやモータウンをはじめとしたソウルミュージックへの傾倒を明確に打ち出していき、人気絶頂の82年に解散、そのままThe Style Councilへと移行する。こちらではポップスやブラックコンテンポラリーをサウンドの基軸に据え、世界的にも、より一般層のファンを獲得していくが(いわゆる”オシャレな音楽”として、日本での人気はこの頃が最盛期かと思われる)、バンド末期は徐々に低迷を見せつつ89年に終焉を迎えてしまう。そして90年からはソロとしてスタート。当初はリリース先もおぼつかない地道な活動ではあったが、95年には3rdアルバム『Stanley Road』が全英1位となり、以降10年は上位ランクの常連である。モノの見事に返り咲いたわけだ。様々な客層というのも、それぞれのタームごとにしっかりと成功を収めたポール・ウェラーならでは現象だろう。なんて思いながら会場を見回していたところで突如の暗転、噴き上る怒濤の歓声。さぁ、いよいよ英国が誇る希代のソングライター、ポール・ウェラーの登場だ!
ド派手な照明がドパッ!というわけではなく、ポール・ウェラーがメンバーを従えて颯爽と!というわけでもなく、さらにはビシッとモッズスーツに身を包み!というわけでもなく…、生の照明(いわゆる普通の暖色系の白)がステージ全体を照らす中、ゾロゾロとメンバーに埋もれる形で登場。ブルーのヘンリーネックTシャツに、グレーにピンストライプのスラックスという出で立ちで。なんともシンプル! 逆にサスガ!と言っておこう。あ、チラッと見えた革靴が黒/白コンビのストレートチップだ! 見えづらいオシャレだ! やはりサスガ!としておこう。でもって、軽く拍子が抜けたコチラの準備もままならぬまま、メンバーが定位置に着くや否や”Five! ジャーン!”というSEが。ツアー最終公演一発目は前作『WAKE UP THE NATION』(’10)から「UP THE DOSAGE」で幕開けである。重厚感のあるマーチング的なビートから始まるストンプ誘発ナンバー。手にしているDwightというメーカーの真っ赤なギターがシンプルな中に映える。最新作のレコーディングではダンエレクトロのギターが活躍したとのことだが、そのキャラを重視してのチョイスなのだろうか。P-90タイプのピックアップ搭載で、音色はブライトかつ程よく枯れた印象だ。身体を上下に弾ませてリズムを取り、それに合わせて鋭いカッティングを繰り出す。ダンスと一体となった動きの中でのカッティングワーク、やっぱりイカす。今度は本当にサスガ!である。続いて最新作『ソニック・キックス』(’12)から「That Dangerous Age」。声にはハリもあり、伸びやかにサビを歌い上げる声には彼独特な渋みのある太さも。連日のツアーの最終日であるが、コンディションは全く問題なさそうだ。音源ではエフェクティヴな音色が飛び交い、デジタル音源のエディットも駆使された楽曲だが、よりソリッドな、バンドサウンドを軸にしたアプローチで聴かせる。その勢いをさらに押し上げるように、3曲目は硬質な緊張感を持った前作収録曲「7&3 Is The Strikers Name」。そしてそして、耳に覚えのある小気味好いリズミカルなベースラインとスクエアなビートが走り始めると会場はドッカン! The Jamのヒットナンバー「Start!!」(5thアルバム『Sound Affects』/’80)だ。そう、今回のツアーでは、ポール・ウェラーのソロ時代だけでなく、The Jamやスタイル・カウンシルの曲も披露するという事前の告知もあって、そこへの期待度も非常に高かった。冒頭ではその貴重なパフォーマンスを狙い澄まして、ダンスそっちのけでステージに釘付け、なんて人も多かったように思われる。とはいえ4曲でアゲにアゲたかと思えば、ギターをエピフォンカジノに持ち替え、97年の名曲「Friday Street」(ソロ4thアルバム『Heavy Soul』)でほろ苦いメロディを会場に響き渡らせ、ググッと落とす。早々に2000人を揺さぶり、大方を掌握してしまった感ありだ。

さて、曲順を追って事細かくレポートしていきたい気持ちもやまやまだが、以降は後述したセットリストを参照していただきつつ、抜粋レポートとさせていただく。アコギに持ち替えての最新作1曲目「ATTIC」と、お待ちかねのスタイル・カウンシル「The Cost Of Loving」(3rdアルバム『Cost Of Loving』/82年)では、それぞれ音源の世界観にさらに、アコギのパーカッシヴなストロークが大陸的なデカさや力強さを楽曲に吹き込む。今回は音源のイメージを損なわないレベルで、ライブアレンジも随所に見受けられた。特に、本編中盤では「WHEN YOUR GARDENS OVER GROWN」や「KLING I KLANG」という最新作『ソニック・キックス』からの楽曲をプレイしたが、最新作を聴いた当初は、サイケというか、強烈にスペーシィなエフェクト・サウンドの洪水にド肝を抜かれた。だが、こうしてライブでより人力の部分がクッキリしてくると、エモーショナルなメロディと、ダンサブルでありながら力強くプリミティヴなリズムアンサンブルのほうがより浮き彫りにされてくる。上モノでは、派手さや”新しいアプローチ”という手触りを与えていても、その根底には確固とした人間臭さ、裸のポール・ウェラーらしさが脈打っているような、そんな印象を痛感させる。
前作からの「Pieces Of A Dream」では本編中盤の一つの山を迎える。同曲でポール・ウェラーはエレピをプレイし(他にも5曲でプレイ)、静と動を巧みに使い分け、美しくエキゾチックな雰囲気からバンド全体がカオティックなセッションへとなだれ込んでいくと、観客は息を飲みパフォーマンスに釘付けに。演奏後にはポール・ウェラーも親指を突き上げGOODサインでバンドメンバーを讃えるほどの演奏の妙に、喝采が巻き起こる。今回のメニューでは比較的短いスパンで緩急の変化が訪れるような流れとなっており、それゆえ一曲一曲の個性が際立つし、演者も一曲一曲が勝負!とばかりに、素晴らしいテクニックを充分披露してくれた。とりわけ、ご機嫌にタバコをふかし踊りながらピアノの位置に着き、これまた聴き覚えあるベースラインで始まった’83年スタイル・カウンシルの名バラード「Long Hot Summer」(1stアルバム『Introducing』)では、音源よりもいなたいベースにダブ的アプローチのギター、そこにピアノとパーカッションの洗練されたフレーズが折り重なるという、より直接的に身体を揺らすようなアレンジでプレイ。スツール(椅子)で身をよじりながら歌い上げるポール・ウェラーも、楽曲の世界観にとっぷり浸かって気持ち良さそうである。ちなみに、同曲中の演奏合間で思い出したように吸いかけのタバコを拾い上げるも、どうやら火が消えてしまったようでスタッフにライターを要求。2000人を前に、近所のパブで演奏しているかのようなリラックスぶりを見せる。いいのか? いいのだ。ここでも演奏後には各メンバーに”今のヤバかったね!”とばかりにGOODサイン。

“そしてライブは、最新作の幻想的かつドラマティックな「Dragonfly」から、本編ラストへと流れを盛り立てられていく。スタイル・カウンシルの活動終焉を経て、ソロ活動をスタートさせる力強い第一歩となった「INTO TOMORROW」(ソロ1stアルバム『Paul Weller』/’92)では、宙に指を差し、その先を見据えて熱く歌い上げる。プレイもさらに研ぎすまされたようにタイトさを増していき、一転して甘美なバラード「ABOVE THE CLOUDS」(ソロ1stアルバム)でのピリッとした演奏、ポール・ウェラーのメリハリの利いた情感豊かな歌に酔いしれる。「FOOT OF MOUNTAIN」(ソロ2ndアルバム『Wild Wood』/’93)では、実に35年に及ぶ世界的ミュージシャンとしての器のデカさを見せつけるかのような、スケール感のあるライブアレンジでシビレさせ、最新作からの「Around The Lake」ではステージ上の6人の息遣いが聴こえるような生々しくヒリヒリするようなプレイで魅せる。そのプレイ、繰り出される音は、驚異的な瞬発力をもって会場の温度を上げいき、素晴らしい本編ラストを飾った。
いやはや、正直ここまで集中して、前のめりにライブを観るのも久々だ。が、困ったことにまだ観たい。きっと会場にいるほとんどの人と同じように。再び登場して繰り出されたスタイル・カウンシルの名盤1st『Café Bleu』(’84)からの「My Ever Changing Moods」では、振り出しに戻ったかのような盛り上がり。波打つ2000人の腕と頭(しかも多くが立派な大人たち)、鳥肌もんだ。その勢いは『As is now』(’05)からの「From The Floorboards Up」でも引き継がれ、フロアは揺れ、そしてそこかしこで共に口ずさんでいる人も。ポール・ウェラーのカッティングの鋭さが”踊れ〜!”と煽るがごく硬質に響き渡る。続くは、サイケデリックな鍵盤とバンド全体で大きなリズムを構築する「PORCELAIN GODS」、同曲を含め、以降は『Stanley Road』の曲で構成し、平和への切なる願いを強く訴える「WHIRLPOOL’S END」の壮大なプレイで会場を包み込む。大喝采の中、アンコールも終了。

鳴り止まない”ウェラー!”コールに迎えられたダブルアンコールでは、牧歌的なメロディが耳と心に染み渡るソウルバラード「Broken Stones」、そして大ラスは、”俺は変わり続ける!”という自身の誇りに満ちた高らかな宣言でもある「The Changingman」で最大の熱量を放出。最後にはメンバー全員が一列となって挨拶し、最高に晴れやかな表情を見せてくれた。
35年の永きに渡る飽くなき探求と挑戦する姿勢、その一つの結論を見せつけられたようなライブだった。この日プレイされた28曲は、メニューの中心に据えられたソロ作品からの楽曲、スタイル・カウンシル時代の曲、ジャムの曲、それぞれがシャッフルされて構成されている。生まれた時代も、音楽的アプローチも様々に違う曲を、新旧、緩急を巧みに使って並べているわけだが、不思議と違和感はまるでない。多少のアレンジの違いや、パフォーマンスの温度による印象の歩み寄りというものも当然あるだろうが、つまるところポール・ウェラーが創る音楽には、大昔から揺るぎない軸がガッチリ根をはっていて、だからこそ思うように、感じるままに枝葉を伸ばせるし、変化に臆することもないのだろう。”どうよ? 筋通ってんだろ?”と、それを証明してくれたような2時間弱だった。小難しく分析せずともロックはカッコイイかカッコ悪いか、そんな潔いもんでいいんじゃない?と言われれば…、ポール・ウェラーは全てにおいて圧倒的にカッコ良かったのである。
[TEXT by GO NEMOTO ]
[PHOTO by SO KURAMOCHI, TSUZIE JACKIE]